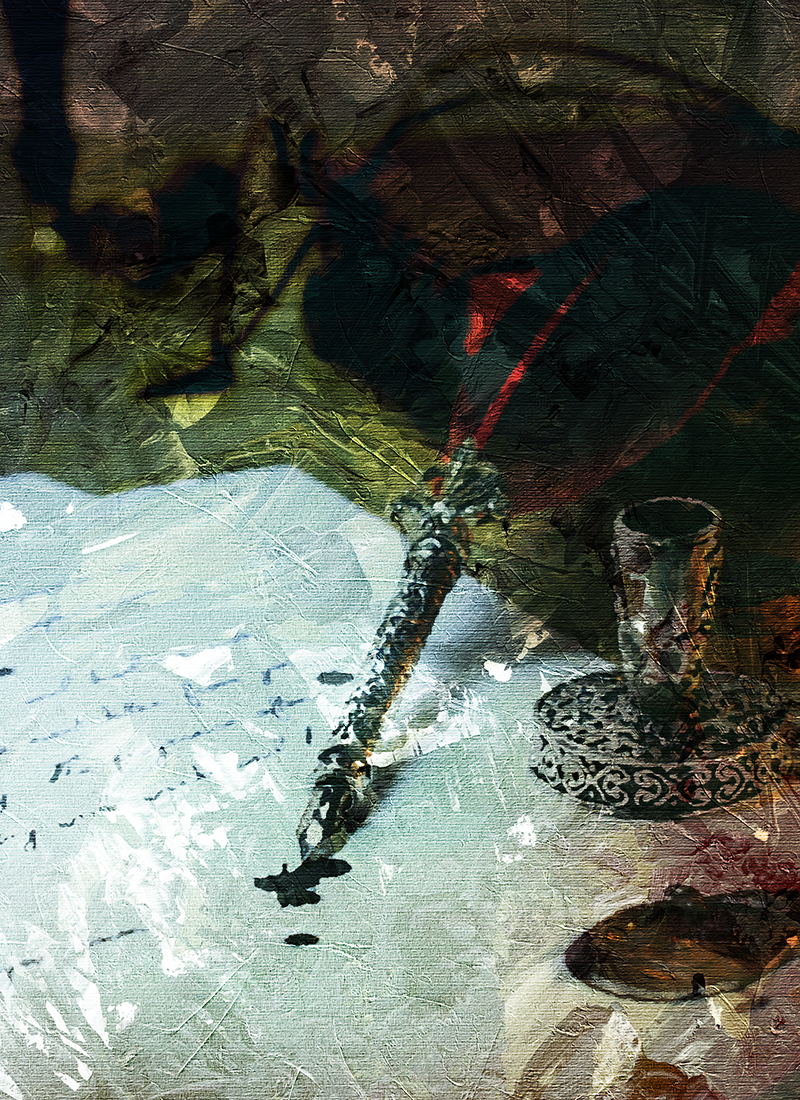早朝の肌寒さの中、一羽の伝書鳩が見張り台に降り立った。
厳重な封蝋を開き、純白の便箋を取り出す。そこには、これより先の海域で海軍が検問を敷いている事、不審船は取り調べを行う事が記されていた。
末尾に押された判は、海軍の物だ。
「随分と律儀なことだ。付き合う必要は無い、迂回する」
「ま、それが無難だよな」
手紙を丁寧に折り畳みながら総士と剣司が進路を相談する頭上、見張り台で双眼鏡を覗いていた操が「あー!」と叫んだ。
「どうした、来主」
「ちょっと遅かったかなぁ」
ほらあれ、と船の進行方向の先を指す。
分厚い霧の向こう、遠くからでもよくわかる文様が描かれた帆を掲げる軍船が、のっそりと姿を現し始めていた。
ただの検問なら、ここで戦闘準備に入る必要は無い。砲弾の扉が開き、ザルヴァートル海賊船に向けて装填の動きを見せていなければの話ではあるが。
「総員、配置に付け!」
船長である総士の父親が、舵を前に右手を掲げた。各々が持ち場へと駆け、側面から大砲の首が生え出す。
霧が薄まっていく。船が交差すれば、それは戦闘の合図だ。海の規律を、海軍自らが破って先制攻撃を仕掛けるような真似をすれば、海賊側も相応の礼をしなければならない。
じりじりと近付き、機を伺う。とそこで、海軍の船から若い男の声が高らかに上がった。
「ザルヴァートル海賊団! 古より名誉ある海賊であると噂には聞いている!」
際に立ち、こちらを見下ろすのはかなり若い将校だ。海に在って金色に靡く髪に、貴族の人間と一目で判断する。
「其方達の船に、真壁一騎が乗っていると情報は掴んでいる。彼女を返してもらいに来た!」
総士の目が丸くなり、甲洋がへぇと口元に笑みを浮かべた。
奪った宝を奪い返しに来たということだ。海賊としての矜持は、それを許すことはできない。
「一騎の知り合いかな?」
「……誰であろうと関係ない」
総士の表情は、怜悧な冷たさを宿す反面、物騒なほど怒りに満ちていた。隣にいるだけで身震いする殺気だ。
「奪えるものなら奪ってみれば良い」
大事にしたいと、離さないのだと彼女に誓った。違えるつもりはない。
すらりと引き抜いた剣を、構える。
「ここまで来たことを後悔させてやろう」
+++ +++
まだ早朝だというのに、どうも外が騒がしい。一騎は、着替えながら首を傾げた。
昨晩は泣き疲れて眠るという醜態を晒した上に、結局総士から是の言葉はもらえなかった。
一騎同様、総士の意志も固いようだ。ならばいっそ行動で示すしかないと、部屋を出て行った総士の目を盗んで、縫い付けられた鍔をナイフで外してみた。
すらりと光る刀身の腹に映る自分。一騎が持っている武器はこれだけだ。今はまだ扱い切れるなんて奢るつもりは無い。腕を磨き、戦えるようになって総士を納得させれば良い。
幸いな事に、教師はたくさんいる。剣司は気兼ねしそうだが、甲洋や操なら頼めば教えてくれそうな気がした。この船は少数精鋭だからこそ、剣の扱いは誰もが一流だと総士の父は言っていた。
着替え終わって剣を鞘に戻していると、今度は妙に静かになった。常に無い状況に、扉の外では何かが起きているのだというのはわかった。
怪物に襲われた時のような、唐突なものではない。これはむしろ、決闘の前に近い、張り詰めた弓の緊張感だった。
ドン、と足の下から振動が船全体を走る。次いで、金属が合わさる音と、怒号に近い叫び声がくぐもって響いた。
人間同士の、戦闘だ。一騎は鞘を握り締め、ドアノブに手をかけた。
(足手まといにはならない……絶対に)
船上が混乱しているなら、隙を見て総士を探す事も可能だろう。なにより彼は、昨日一騎を庇って怪我を負ったばかりなのだ。弓は引けない。遠距離の攻撃を得意としている彼の最大の武器は使えない状態のはずだ。
(……総士を、助ける)
意を決し、扉を開けた。
+++ +++
戦闘開始を告げる砲撃と重なるように、海軍の戦闘員が続々と此方の船に乗り込もうと甲板を蹴った。
遠距離の部隊が正確に撃ち落としてゆくものの、やはり数人は看板に着地して、すぐさま刃を交わす音が響き始める。
総士は合間を縫うように身体を滑らせ、目的の男の元へ駆ける。嫌味かと思うような美しい剣捌きを披露する男に、総士は剣を振り上げた。
荒々しい金属音を響かせながら、男が刃を受けとめる。それ以上押してもびくともしない。体幹が鍛えられている証拠だ。
「くっ……」
互いに距離を取るため飛び退く。二人の周囲だけがやけに凪いでいた。
「私は、ジョナサン・ミツヒロ・バートランド。海軍特務兵第一分隊隊長を務めている。貴殿の名は」
「皆城総士。ザルヴァートル海賊団第一隊隊長だ」
対局に位置しながら似た肩書というのは皮肉なものだ。
ジョナサンと名乗った男には、貴族にありがちな高慢さと驕りが無い。戦い辛い相手だ、と心の中で舌打ちする。
「真壁一騎はどこにいる」
「貴様に教える筋合いは無い!」
横から剣を一閃。軽い身のこなしで避け、ジョナサンの一撃も総士を擦る事なく打ち合いが続く。
入り乱れる戦闘の中で、総士が繰り出す攻撃をいなし、正確な一撃を繰り出すジョナサンは型通りの正攻法だ。海軍仕込みの攻撃は奇策には弱いものの、真正面の対決となるとその真価を発揮する。
実力は拮抗しているが、怪我をしている分総士の方が不利だ。早々に片をつけるべきだが、ジョナサンの剣捌きは予想より遥かに洗練され、一撃は重かった。
二度三度と剣を交えては離れ、先に息が上がり始めたのは総士の方だった。
片腕を庇うような状態で戦えば、疲労の蓄積は増す。それを理由にするつもりはないが、昨日の今日では完治しているとは言い難い。腰を落としてなるべく隙を与えまいとしても、目に見える形で疲労が表れてきてしまっては自ずと隙は生まれ。
一瞬の攻防は、攻撃を受けた総士がジョナサンの一撃を受け止めきれず眉を寄せた瞬間に決していた。
総士の剣が宙を舞う。痺れる腕を抱え、後退する。
「怪我をしていると見受けます。命が惜しければ、こちらの要求に応える方が賢明かと」
「残念だが、海賊は奪った宝を譲らない。それが命に代えても守りたい存在なら、尚更だ」
「……」
切っ先を下ろし、ジョナサンは訝し気に総士を見つめた。そこに誰かの面影を見探そうとするかのように、目を細めて。
「まさか、あなたは……」
言いかけ、代わりに二人の間に身を滑らせたのは、この戦闘の発端である存在だった。
「総士!!」
黒い髪が、ジョナサンの前に立ちはだかる。何故此処に来たんだという非難を込めた視線を受けても、一騎は構うことなく総士を庇うように腕を広げ、ジョナサンと相対した。
「一騎、やはり此処に居たのですね」
「ジョナサン……」
総士に向けていた顔とは一転して、喜びに綻ぶ双眸。気安い仲を思わせる声色に、一騎への独占欲が胸の中で渦巻く。
「半年前あなたが攫われて、それが海賊の仕業であると目撃した商船がありました。海賊船は航路を定めないから、探し出すのに半年もかかってしまった」
「俺のこと、ずっと探してくれてたのか?」
「当たり前です。あなたは、俺の大切な幼馴染みだ」
友人を助けるのは当然だ、と一騎の手を握る。懐かしい、一騎がよく知る手だ。
総士のよりずっと柔らかくて、昔から一騎のことをよく理解してくれようとした彼の手。
「帰りましょう。お父上も心配されています」
「父さんが……」
「アイも、もちろん私も。結婚については先方が破棄を申し入れました。あなたは、ちゃんと島に帰ることができる」
島に帰る。故郷に。愛する家族の元に。
郷愁はいつだって一騎の中に在った。帰りたいと思ったことだってある。海の上の生活は決して楽じゃない。決まったことなんて何もない。
ここでジョナサンの手を取れば、元の生活に戻れる。父と、友人たちと暮らすあの島で、きっと一生を終える。それもまた懐かしい、優しい暮らしなんだろう。
でも、と一騎は振り返った。
灰色の瞳が、辛そうに一騎に注がれている。行くな、と雄弁に語る傷付いた瞳が、たぶん一騎には愛おしくてたまらないのだ。
初めは憧れだった。約束の証のように、綺麗なガラスに収まった狭い世界の話だった。けれど、総士は世界に連れて行ってくれた。世界を知って、今を知って、未来を歩みたいと思わせてくれた。
総士が何を考えているのかわからなくて、自分がこの船にいる意味が欲しかった。総士の手を借りずとも船の上で自立した人間になりたい。だから、戦う術を求めた。そこに自分の存在意義があると思って。
その想いは変わらない。総士が許さなくても、一騎は力が欲しい。総士の隣に並び立つに相応しい力が。
「……俺、帰らないよ」
ジョナサンの手を握り返して、祈るように言葉を紡ぐ。
「父さんには悪いんだけど、俺はここで、総士たちと暮らしたい。十年前の約束を忘れずに叶えてくれた、大切な人のもとで」
「やはり……彼が、あなたが探していた人だったのですね」
「うん。迎えに来てくれた」
微笑むと、ジョナサンは寂しそうに眦を下げた。
一騎は、幾度となく総士の事を話していた。名前も知らない男の子と、いつか世界を旅する夢を。
「海賊です。それでも?」
もっともな問いに、一騎は首を縦に降る。
ごめんと伝えるのは筋違いな気がして、手を離した。
「……わかりました」
す、と一歩下がったジョナサンが、剣を構える。
その切っ先は、一騎ではなく、後方で成り行きを見守っていた総士に向けられて。
「――総士っ」
反撃に転じようとしていた総士の身体を押し退け、腰から短剣を引き抜く。
ジョナサンが振りかぶった剣を受けとめようと頭上で構え、ひゅうと風を切る音と総士の悲痛な叫びが一秒にも満たない間に交差した。
切られたら痛いかな、と想像して目を瞑った。ただひたすら総士を守ることだけを考えた。
総士の手が、柄を握る一騎の手を覆う。え、と間抜けな吐息が零れ落ちて瞼を開くと、総士を貫こうとしていた刃が一騎の剣と交差することはなく、既に鞘にしまわれていた。
「ここに、一騎の幸せが在るのなら」
「ジョナサン」
「引きましょう。船の点検は終わりです」
くるりと踵を返す幼馴染みの背中。
追いすがりそうになる一騎の腰を抱いて、総士は低く唸った。
「礼は言わない」
「いりません、そんなもの。それより、一騎を必ず幸せにしてください」
「言われるまでもないな」
総士の返事に満足したのか、一瞥だけを残して船から引き上げるよう指示を出す。
大方、目的の人物はいなかったとして処理するのだろう。一方的に海賊船を捕えたり沈めたりすることは、海軍の中では黙認されている。総士達が宣戦布告でもしなければ、『無かった事』になる。
そこに決別を感じ取って、一騎はたまらず離れていく背に声をかけた。
「ジョナサン!」
幼い頃から共に育ち、いつだって一騎を心配し気にかけてくれた友達。もう二度と会う事はないかもしれない。会えば、敵になっているのだから。
「アイと、幸せに」
ふ、と微笑みを浮かべ、ジョナサンは朝靄の向こうへと消えていった。
ありがとうと言うのはおかしいかもしれないが、一騎の意志を尊重してくれた彼に、これから多くの幸と愛する人との未来が開かれている事を願った。
嵐のように過ぎ去った戦いの余韻。甲板の上はひどい有様だが、死人は出ていない。本当に一騎だけを目当てにしていたようで、ただ酒の樽に穴を開けられて何人かが許せないと悔しがっているくらいだ。
「一騎……」
背後で、総士がぎゅっと一騎の頭に顔を埋める。
「頼むからあんな真似はするな」
「もうしないよ。さすがに無茶だったかなって思った」
「まったくだ」
疲れた様子で溜息をつき、ぐりぐりと額を押し付けられて痛い。正面に回った手を叩いて抗議していると、良かった、と心から安堵する声に胸が締め付けられた。
「……総士、俺、やっぱり戦えるようになりたい」
「一騎」
今の流れで何をほざく、と言いたいのだろう。
咎めるようにきつくなる視線から逃げずに、一騎も見つめ返す。
「総士が教えてくれないなら、甲洋や操に頼む。剣が使える人は他にもたくさんいるから、二人が駄目なら皆にお願いする」
「僕は賛成!」
しゅるるとロープを伝って降りて来た操が、ウィンクを一つ。
「一騎、絶対鍛えれば強くなるよ。皆もそう言ってる」
「来主! 余計な事を言うな!」
「残念だけど総士、この船で生き残るにはやっぱり戦える術を身につけるべきだと思うよ」
「甲洋」
血が付いてしまったのだろう、刀身を布で拭きながら甲洋も賛成の意を表す。
目が輝く一騎に対し、忌々しいと眉を寄せる総士は、やがて大きな溜息と共に一騎の腰に回していた手を解いて反転させ、肩を抱いた。
「僕の目の届かないところでやられるくらいなら、僕が教える」
「ほんとかっ」
「ただし、僕が許可を出すまで強くならなければ、一人で剣を持つのは絶対に駄目だ」
「ああ、ありがとう総士!」
嬉しいと抱きつかれ、虚をつかれた総士の顔が赤くなる。
今まで散々身体を重ねるようなことをしていたのに、変なところで初な反応を示す未来の船長に生暖かな視線が送られる。が、当の本人たちは全く気付いていない様子で二人の世界に入っていた。
お腹減ったと操が騒ぎはじめ、一騎が慌てて厨房へ走り、いつもの朝が始まった。
+++ +++
「この香水、すごく良い香りなの。一騎も良かったらつけてみて?」
そう言って手渡されたのは、乙姫が好んでつけているという香水だ。
朝方の戦闘で損傷した船を整備していたら一日が暮れてしまい、夕飯を終えた船内はほどよい活気と夜への備えが始まっていた。
船乗りは酒飲みが多い。この船に積まれた飲み物も半分は酒で、それは船を安定させるための重石の役割もあるのだという。
剣司も甲洋もよく飲む方だが、潰れるのが早い。操は未成年なので許されておらず(とは言え海賊に禁酒の年齢などあってないようなものだが)、もちろん乙姫はぶどうジュース。
総士は顔に出にくい酒豪で良い酒を少しだけ飲むのが好きらしい。酔い潰れるような飲み方はしない、と酔い潰れた面々を前にして言っていたので、何か酒関連で嫌な過去でもあるのかもしれない。
今日も早々に自室に戻ってしまった。後片付けを終えた一騎が厨房を出たのはすでに満点の星空が夜空を照らしている時刻。乙姫にもらった香水を手に、総士の部屋へと急いだ。
一騎の部屋は無い。そもそも狭い船内で、一人部屋を与えられているのは総士と乙姫、そして船長だけだ。他の船員は大部屋に雑魚寝か、ハンモックなどが自分だけの場所、となる。
この船に連れてこられた日から、総士の部屋が一騎の部屋であり、私物は買ってもらった洋服くらいで、化粧道具はほとんど乙姫から借りていた。
「いいのか?」
「うん。気に入ってもらえると嬉しいな」
じゃあ頑張ってね、と手を振られた。あれは何を頑張るんだろう、と首を傾げるが特に気にする事なく手首に軽くふってみた。
甘さの中に僅かな酸味を混ぜた優しい香り。女性らしいのかはわからないが、乙姫が選んだだけあってきつすぎない程度に香るもののようだ。せっかくなので首にもつける。
総士も気に入るだろうか。少しだけ期待して部屋に戻ると、ベッドの上で地図のようなものを広げて難しい顔をしていた。
「何してるんだ?」
「次の目的地を考えておけと父に言われていたのを思い出した。季節の関係で潮流の流れが南に向いているから、そちらを通るのも悪くない」
ベッドに乗り上げて、紙片を覗き込む。よくわからない動物なのか、魚なのかの絵が所どころ描かれ、方位と名前が書き込まれたそれは世界地図と呼ばれるものだ。
大陸ではあまり出回っていないが、海賊はそれぞれの船が航路図を作って航海に必要な情報を書き込んでいくらしい。そのためにも、測量士や地学に明るい者は重要で、この船では五人、その役目に当たる人がいる。
「南は、どんなところなんだ?」
「そうだな……まず、木の形が全く異なる。より水分を含み易く、果実が成る木も多いな。あと、海の色が濃い」
「へえ」
「食べ物は暑さでも保存に適した薫製や、干した魚、あと果物や野菜が豊富だ。生ものを食する習慣はあまり無いと聞く」
総士の知識は底なしではと思う程で、次々と地形から気候、暮らしぶりまで語ってくれた。実際に目で見るのも面白いが、総士の話を聞くのも好きだ。十年前も、あの秘密基地で彼の言葉に耳を傾けた。
地図を挟んで話を聞いていたが、隣に座っても良いだろうかと思い立ってもそもそと傍まで移動した。どうした、と聞かれて、なんとなく、と答えれば、そうかとだけ返ってくる。腕を引かれ、密着すると、先程の香りが空気に漂った。
「……香水でもつけているのか?」
「うん。乙姫がくれた」
手に持ったままだった香水瓶を渡すと、ラベルに目を通していた美しい灰紫が固まった。
「総士?」
「……あいつは……」
まったく、と瓶を枕元に投げて地図を乱雑にたたみ始めた。やけに焦った様子で机に置き、ベッドに座ったままの一騎に覆いかぶさる。
「んっ……総士」
「この香水の成分に含まれる、ガーベラの花言葉を知っているか」
「花言葉……」
「色によって意味は変わるが、総じて愛を伝えるためのものだ」
素肌を這う総士の指が滑らかな鎖骨に添えられ、後を追うように吸い付く。首筋の香りを楽しみながら、一枚ずつ服を肌蹴させていけば一糸纏わぬ姿にするのは容易だ。
「これが返事でいいか」
「へん……じ……?」
「愛している、と言っただろう?」
ふ、とか細い息を吐き出した一騎の頬が上気して、目元を染めた。
「……好きだよ、総士」
はじめて贈る、一騎からの愛の言葉だった。
総士の首に手を回して、誘うように瞳を閉じる。
唇を重ねると、今までしたどのキスよりも優しくて甘いそれに酔いそうだと、二人してより深くを求めあっていった。
+++ +++
とぷりと波の音が鼓膜を震わせ、瞼を開いた先には朝と夜の間を思わせる色が一騎を見下ろしていた。
詰めた息が時折頬や首筋にかかり、くすぐったさに身を捩るとまた波の音がする。
「……一騎、痛くはないか?」
「ん、だい、じょぶ……総士は……?」
「僕?」
「腕……」
これか、と包帯の巻かれた左腕を掲げる。少しばかりの沈黙の後、口の端に笑みを乗せて右胸の頂きを親指で刺激した。
「やっ……」
「問題ない。痛みももう引いた」
舌先でもう片方も押しつぶし、ちゅぷ、とわざと音を立てて口を離す。悩ましげに眉間を寄せた一騎の両手をシーツに縫い止めて、中を穿つ。
ぐ、と押し込まれた熱が一騎のイイところを掠め、奥深くにまで総士を感じる。背を走る快感に思わず仰け反っていると、律動が再開した。
「あっ、ん、ふぁ……!」
ずぷずぷと耳を塞ぎたくなる音が自分から発されているかと思うと羞恥で顔を覆いたくなるが、そんな余裕もないほど中に穿たれた熱が一騎の意識を曖昧にさせていく。
こんなに濡れるのも、気持ちいいのも、身体を繋げてからはじめてだ。総士が与えてくれる全てを拾いあげようと全身が溶けてぐすぐずになっていく。
「い……いぃ、きもち、い……っ」
音にすると、湿った音がさらに潤いを増した。繋がった手が痛いほど握り締められて、このまま総士と一つになるんじゃないかと思うと一騎は嬉しくてたまらない。
「……っ」
と、不意に総士が息を詰めた。中でびくりと波打つ熱に目を瞑ったら、宙に浮く不安定な感覚がして総士の手を握り返す。
「ひぁ、ああああッ!?」
中に入ったまま身体を反転させられ、一騎から悲鳴にも近い嬌声があがる。
背後に回った総士が腰を高く上げるように体勢を変えて、真上から硬度を増した起立を突き下ろした。
「んぁ、あ……!!」
目の奥がちかちかして、這い上がる快感を枕を噛んでやり過ごす。強すぎる衝撃に声も出せず、首を振れば溜まった涙と唾液がパタパタとシーツにシミを作った。
総士は一心不乱に腰を打ち付け、引いては押し込み、胎を総士の形に広げていく。
「や、だめぇ……」
「何が駄目だ」
背中がぴっとりとくっついて、耳に吹き込まれる低い声に肌が粟立つ。
最早言葉にならない途切れ途切れの音で、精一杯伝えようと口を開くのだが、その度に中が蠢いて喘ぎ声に変わった。
「あぅ、や、おくぅっ」
「もっと奥に欲しいのか」
しかたのない奴だ、と嬉しそうな総士の声が脳髄を麻痺させて、一度抜けそうなところまで抜かれた起立。一息に深いところを容赦なく突き上げ、抉り、攻め立てた。
「ぁあうっ……も、イ……ッ???!!」
ぐぷんと奥の奥に嵌め込んだような感覚と共に、声を出すこともできないほど強烈な快感がせり上がった。
びくんびくんと腰を中心に痙攣が全身に広がり、胎の中で総士の熱が弾ける。
「ふあ、くっ……」
感極まった背後の声に一騎の中が締まった。余す事無く注がれる精を強張るかのように内壁が絡み付く流れに逆らうことなく、断続的に中を満たしていく。
ずるりと崩れ落ちた姿態。余韻が残っているのかまだ焦点を結ばない瞳がどこかを見つめ、荒い息が艶めかしく部屋に響いた。
一騎を、ひたすらに愛した人を手に入れた、その想いは一度の交わりで収まる筈も無く、むくりと欲が下腹部に集まりつつある。
「一騎、もう一度したい。いいか?」
訊ねると、ゆっくりと振り返った琥珀色の双眸が総士を見上げて「顔、見たい」と可愛らしいおねだりを請う。
「総士の顔見て……きもちよく、なりたい」
「??…お前は、そういう事を……」
舌足らずなお願いを聞き届けるため、手早く腰の下にクッションを敷いて入り口に先端を擦り付ける。正面から互いの顔が見えるように、一騎からは総士の顔しか見えないように、緩く抱き締めて、再び胎内に押し入った。
「んく、あ……そうしの、あつ……!」
「お前の、なかも……はっ、全部、持っていかれそうだ」
「ちょ、だい……中、いっぱいに、してっ」
粘液と空気が混ざり、泡立つ音が激しくなっていく。
互いの境界線が曖昧になるくらい肌を合わせるのが、こんなに安心するなんて知らなかった。きっとそれは、総士が一騎を求め、また一騎も総士に許しているからなのだと思うと叫びだしそうなくらいの幸せで満たされる。
淫らな音が耳の奥に反響して、総士から与えられる全てに胸がいっぱいになって。それなのに足りない。底の見えない海のようだ。
一騎が嬌声をあげる度に、総士も気遣いなど捨て去って本能のままに揺さぶってしまいたくなる。もう無理だと涙を流すまで注ぎ込んで、自分のものだと刻み込んで支配したいと。
「……そ、し……あっあっ!いぁぁあ!!」
「ここ、か……っ?」
「そこっやぁ!ぃ、おかし、く、なるぅ……!」
それでもいつだって一騎への愛おしさが勝る。気持ちよくなって欲しい。自分だけがこの快感と陶酔を齎せるのだと、総士だけしか受け入れない身体にしてしまいたい。
一騎の泣き所をぐりぐりと攻めれば、涙を溜めた瞳が大きく見開かれて、とろりと樹液を垂らした琥珀から眦を伝う。
美味しそうに思えて、舐めるために身体を折り込むとついに一騎が限界を訴えて総士の背中に爪を立てた。
「いく、あ、いきそっ……!」
「ああ、一緒に……」
「そ、し……ぁ、あぁっ」
「大丈夫、だ……ぅっ……イけ、一騎……ッ!!」
一番に感じるところを突きこまれ、背をピンと仰け反らせたまま一騎が達したのと、総士が熱を吐き出すのは同時だった。
二人で一緒に果てるのもはじめてだとぼんやりとした意識の中で思う。今日は、はじめてのこと尽くしだ。
「かずき」
弛緩した身体を労うように細い指が髪を梳く。しっとりと水分を含んだ黒髪に口付けを落として、今度こそ硬度をなくした起立を抜き去って豊満な胸に吸い付いた。
「ふぁ、そうし……くすぐったい」
赤い華を幾つも散らしながら、欲を追うのではなく微睡みに愛撫を施す、ゆったりとした触れ合い。一騎の腰に腕を回したまま、総士がぽつりと呟いた。
「僕のそばにいろ、一騎」
「総士?」
腹に掌を当て語りかける様子に、どくりと、心臓が鳴る。
「皆城の跡継ぎを、ここに宿して欲しい」
顔が熱い。きっと頬は真っ赤だ。総士の真摯な瞳が、じんじんと胸を焦がす。
「これからも共に生き、世界を旅したい。だから、僕を選んでくれ」
「……総士」
はじまりは、小さな約束だった。
それは夢となり、憧れとなり、現実となった。
今、彼の手を取ることを選んで、一騎に後悔はない。一騎にとって総士は、誰よりも愛しい人になったから。
「俺で良ければ、喜んで」
屈んで唇を合わせる。手を添えた総士の頬は少し冷たくて、一騎とは正反対。
くるりと丸くなった灰紫の虹彩が「本当に?」と揺れる。
一騎は、心の底からの笑顔を浮かべた。
「愛してる、総士」
この言葉を、この人に贈れて良かった。
これから何があるかなんて分からないけれど、総士と一緒なら、なんだって乗り越えられる気がする。幸せになれると思う。
だから、同じくらいの幸せを総士にあげるのだと、一騎は決めたのだ。
ぐい、と引き寄せた唇にもう一度。今度は軽く啄んでみたら、おかえしとばかりに深く舌を絡めあった。
窓辺に置かれた海のお守りが、大海原の太陽の光を受けて二人を祝福するように輝いた。